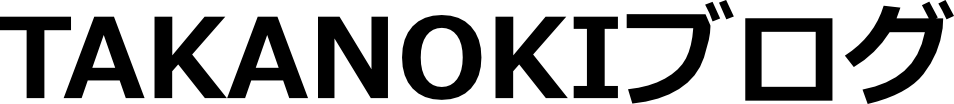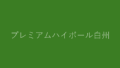この記事では、私がブログ運営で失敗したこと5選を紹介します。
失敗をベースとした記事なので、反面教師として活用できます。
戦略上の失敗を3つ、マネジメントの失敗を2つ紹介します。
戦略上の失敗 3つ
戦略上の失敗においては、致命傷になりうる3つを厳選して紹介しています。
とにかく大量投稿 数を打てばいいという思考

たくさん記事を投稿して、認知度向上 → 品質の高い記事を生産する といったサイクル
記事をたくさん投稿することが目的化 → 記事品質が低下し、挙句の果てに記事削除
ブログを始めたての頃は、とにかくたくさん記事を書くことに慣れよう、と言われがちです。
これは、間違いではないと思います。
なぜならば、活動初期はGoogleや読者に認知されるほどの情報を、記事として公開できていないためです。
ブログ初心者の場合は、投稿に慣れるという観点から記事をたくさん投稿したり、書くのは理にかなっています。
また、Googleに評価してもらう、という観点からも記事数は重要かと思います。
書くことに慣れるのと、記事数を増やすのは理にかなっている
しかし、記事をたくさん投稿するのは、とにかくキモチよいものです。
世の中に情報発信出来て、承認欲求が満たされたような感覚になり、痛快な気分になります。(私の場合はそうでした)
ただ、面倒なのが、一種のオレってスゲーみたいな勘違いを引き起こした点です。
記事を投稿することが目的化し、自分のキモチいい、が優先されてしまっていた節があります。
大量投稿できる自分に酔って、記事の中身を蔑ろにし、挙句の果てには痛くなって記事を削除。
大失敗。
これと真正面から向き合うのは正直しんどいので、正当な理由をつけて心理的安全を図っていました。
この行動が私の内省の機会を減らし、もっともらしい理由をつけて、自分は正しい行いをした、という正当化に至ります。
記事をたくさん書くことで、自分はすごい、という勘違いをした。それが、自分の内省の機会を減少させた。
数をたくさん打つというのは、一つの戦略です。
しかし、使い手によっては、痛い結末を迎える可能性もあります。
SNSと連動させて集客をする

露出を増やし記事アクセスが増える可能性あり
単純に記事を投稿したというアナウンスをするBot(自動で投稿する機械)と化してしまった
反省ですが、フォロワーを獲得する意識が全くありませんでした。
これでは、SNSを使っている意味がありません。
記事をブログに投稿したら、SNSに記事投稿した旨を書き、投稿していました。
SNS上でなにか交流するわけでもなく、ただつぶやいて終了。
時間のムダでした。
たまに、「いいね」がついたりしますが、継続的フォロワーの獲得には至らず。
SNSに対する私自身の改善も見受けられず、億劫になりそっとSNSから身を引きました。(SNSに投稿をしていない)
SNS活用の具体策を学ばなかった。SNSを継続しようとしなかった。
テンプレを意識した記事生産
テンプレをベースに記事を効率的に書くことができた
テンプレを意識しすぎ、記事を作る事ばかりに注力してしまった
私は記事投稿するにあたって、自分の中で決めている型(テンプレ)をベースに記事を書いていました。
型にはめて記事を書くことで、生産力は向上します。
実際に、限られた時間で品質は悪いながらも数は生産できていました。
しかし、このテンプレに当てはめすぎると自分でテンプレに対して疑問を持ったり、改善しようという思考に至りません。
マネジメントの失敗 2つ
ここでは、個人ベースのマネジメントの失敗を取り上げます。
具体的には、自己管理に起因する2つの失敗事例を列挙します。
モチベーションに頼る

モチベーションが湧いてる(やる気がある状態の)ときは、活用すると効果的
モチベーションが湧くまで行動しない状態が続くと、いつまで経っても行動できない
モチベーション(以下、「モチベ」と表記)に頼るのは良くも悪くも、気分に頼るということになります。
気分に頼ると、「やりたくなければ、やらない」という弊害が生じます。また、モチベが湧くまで行動しないという悪循環に陥ります。
たとえ自分の気分がどうであれ、時間をとって記事を書く仕組みが必要です。
ハッキリいうと、記事を書かない方が圧倒的に楽です。私は、ある時からまったく記事を書かなくなりました。モチベが湧くまで待っていようと考えたわけです。
YouTubeやアニメを見たりして、時間を浪費し、楽な選択肢を選んでいました。
気付けば、長期的にその状態が続いていました。でも、まったくブログへのモチベが湧いてこない。待てど暮らせどモチベは湧きませんでした。
モチベが湧くまで待ち続ける
教訓ですが、モチベは自然に湧かないです。始めないと湧かないです。
余談(飛ばしてもOK)
余談ですが、モチベが湧かずにブログから遠のいた人間(私)の姿を知りたくないですか。
何もかも無気力で、自分からアクションを起こさない、こじらせて、冷笑系傍観者となり、挑戦しない。
ブログに対する考え方が歪み、自身を正当化することに奔走します。自分ができないのは自分のせいではないという他責的思考が芽吹きます。
こうなると、ブログを書こうという思いにすら至りません。
私は3か月くらいこじらせて、ようやく再挑戦しようと思えました。
ブログを書く習慣をやめてみた感想は、やめるのは簡単で、再挑戦するのは難しいということです。
自分のやらかしを失敗と認め、向き合う勇気はかなり精神的につらいものです。
しかし、この偉そうな「ブログの失敗5選 ブログの失敗事例から学ぶ」とかいう記事を書いているわけです。
超うさんくさいなぁ…と思いながら書いています。
でも、成功者の物語よりは、敗北者の失敗の方が身近で役立ちそうなので、反面教師にしてください。
何かと言い訳をしてブログを書かない
一文字でも記事を書いてみる スタートしてみる
記事を書かないことで、ブログから遠のき、言い訳を通じて自己正当化してしまう
ブログを書かない理由は、いくらでも挙げることができます。
しんどい、時間がない、やる気がでない、意味を感じない、批判されたらどうしよう、大手と比べたらこのブログなんて…
ブログを書かない弊害は、ブログと距離が遠くなることです。
距離が遠くなれば、関心が薄れます。
関心が薄れ、記事を書く習慣が失われてしまえば、目標だった記事数を達成できません。
さいごに
さて、私のブログの失敗事例を紹介してきました。
特にマネジメント的な失敗は自己管理の甘さにあります。
管理せずとも仕組みとして記事が書けるようにしておくと、記事生産も安定化すると思います。
戦略の失敗は、使い手(私)の使い方に問題があるケースが主でした。
自分にあう戦略を見つけるために、ほかの人のやり方を真似したり、方法を学んで実践し、自分に合うものを見つけるのも一つの手だと思います。